スポンサードサーチ
目次
泥酔した女性とべんの物語

こんにちは!べんです。
いつも行くカフェでカフェラテを頼むのですが、店員からラテマンと呼ばれているのでは?
と疑心暗鬼になってます。
今後、継続して、意地でもカフェラテを頼みたいと思います。
さて、今日はべんととある女性たちの物語を書きましょう。
甘酸っぱい、そして少しだけドキドキするそんな物語です。
べんはミューズに遊びに行きました
冬の寒い日だった。
吐く息の白さが気温を物語り、強い風が僕の髪の毛を揺らす。
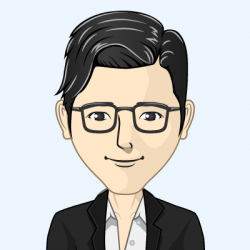
彼は『K』。クラブに行くときはいつも一緒だ。
並んで歩いているKが、今日は少しだけ頼りがいがあるように見える。
なぜならば、彼はミューズを自らの庭と自称しているからだ。
スポンサードサーチ
ミューズに到着したのは2:30頃でした。
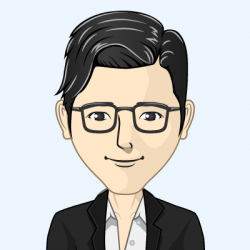
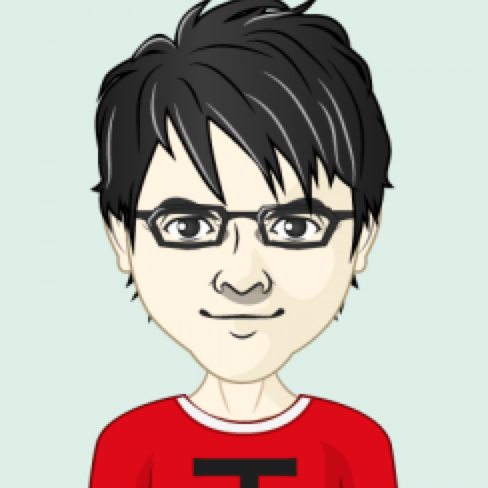
彼は僕を心配してくれていた。
いつも、何食わぬ顔をして、誰とも喋らず、踊って帰る僕のことを気にかけてくれていた。
彼は勘違いしてるけど、僕だって、誰かと話したりする。
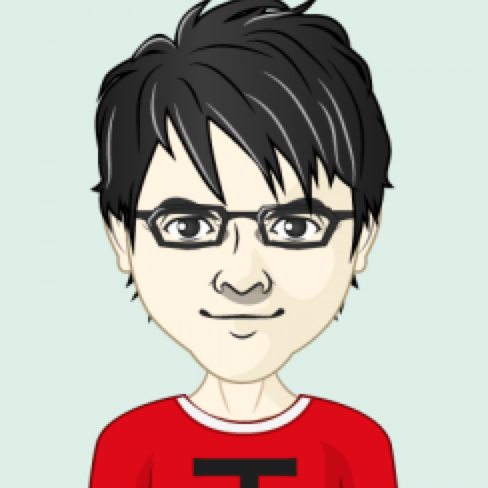
こんな風に誰かとぶつかったときは会話をしている。
もちろん、相手から何か言われることはないが、それでも僕にとっては重要な会話だ。
その日も、例のごとく、『K』が仲良く女の子と話をしている。
気を使って彼は僕のことも呼んでくれるが、誰とも会話をしないのに、グループの中にいると僕の孤独感が増すことを彼は知らない。
いつものように、自分の存在を消し、その場を立ち去り、僕はDJブース前に移動した。
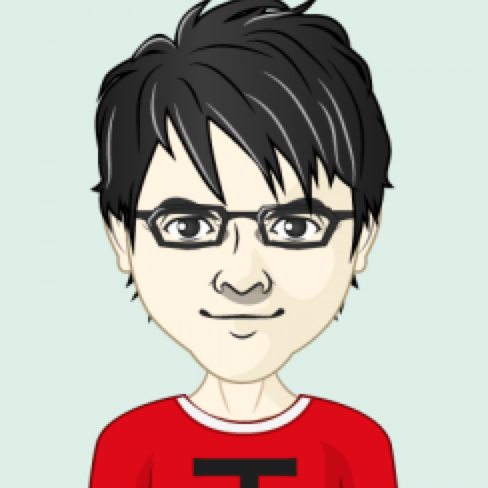
何か忘れたようにはしゃぐこの時間が僕は好きだった。
誰かと話に来たのではない。僕は踊りにきたんだ。
だから、誰かと話せなくても気になんかならないんだ。
その時間はとても楽しい。これは嘘ではない。
ただ、その時間はいつも突然訪れる。
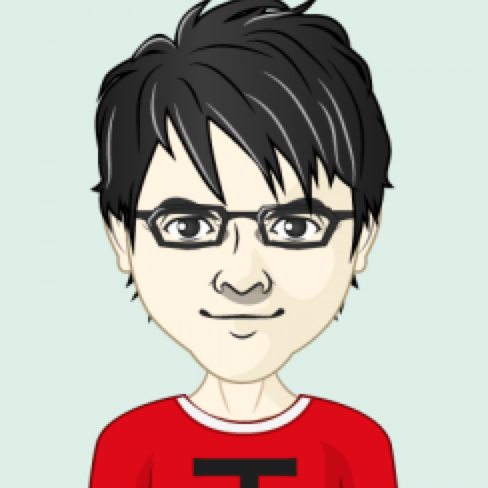
この事象の最も恐ろしいことは、ふとひとりぼっちでいることに気づかされたことだ。
踊っているときは楽しい。間違いない。
しかし、踊り終えたあと、一人で仲睦まじい男女の後ろに並び、飲み物を買おうとするそのとき。
とてつもない孤独感は襲ってくるんだ。
感覚を遮るメリット
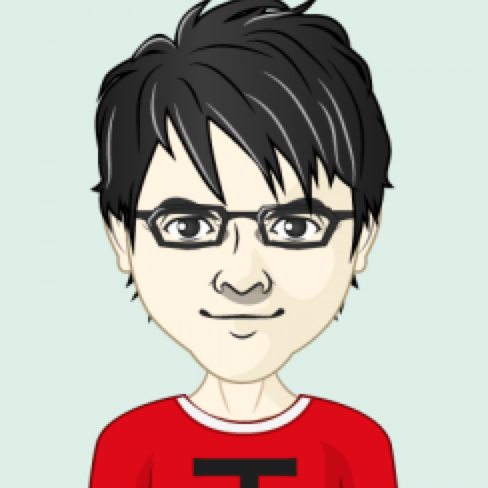
バーテンにそう頼み、ポケットの中のドリンクチケットを探す。
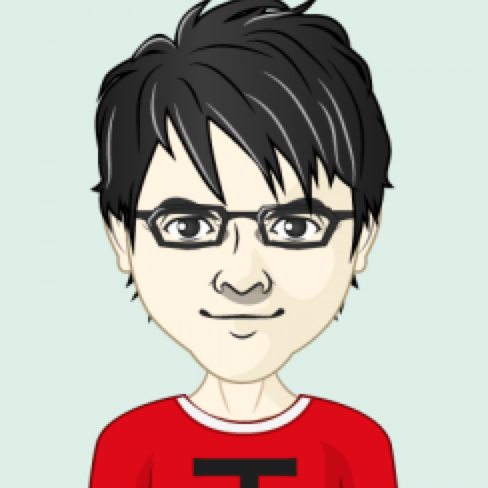
僕は例のごとく、ドリンクチケットを落としていた。
ポケットの中にも財布の中にもない。
誰かが、僕のドリンクチケットを拾って、何か飲んでくれたのだろう。
僕じゃない誰かが得をした。僕が損をした。世界の『幸と不幸』はプラスマイナス0だ。
そう自分に言い聞かせ、僕は財布から1,000円取り出し、バーテンに支払いをした。
一人でお酒を飲んでいる。
音楽を聴きながら、目をそっとつぶる。
まるで、自分だけがクラブにいて、DJが音楽を流してくれている。
そんな妄想を一人でして、その時間を楽しむのが僕にできる唯一の抵抗だった。
人の感覚の9割を司る視覚をそっと閉じてあげることで、僕の心の孤独感も9割減になっているに違いない。
あくまで理性的に自分の心情を分析しているときに、その出会いは訪れた。
スポンサードサーチ
突然の出会い。

それは突然の出会いだった。
僕が女性に声をかけることはもちろんだが、かけられることなぞあり得ない。
ネズミ講?マルチ?宗教の勧誘?生命保険の営業?
様々な憶測が僕をよぎったが、それ以上に僕はうれしかった。
数百人が踊るこの場所で、たっと一人で過ごす孤独感と比べれば、内容に関わらず話せる人がいるのはうれしかった。
僕は彼女に心当たりはなかった。
ここでは彼女のことを『ゆか』と呼ぶことにしよう。
『ゆか』は以前にほかのクラブで僕と飲んだことがあったようだ。
詳細は控えるが、複数人のグループで一緒になって楽しんだらしい。

そのときに僕の中でひとつの答えが出た。
おそらく酔っぱらって僕は覚えてないんだろうな。と。
恥ずかしいことに、僕は類に見ない酒癖の悪さを誇る。
暴言や暴力を振るうなどはしない。
ただ、酔っぱらってわちゃわちゃしちゃうのだ。
そして、普段のリミットが外れたように、人と喋ることも躊躇をしなくなる。
女性と連絡先を交換することに成功したときはいつもそうだ。
その代償として、記憶と、後日会ったときの印象が大幅に変わるという弱点も兼ね備えている。
まさに諸刃の剣と言ってもいい。
僕は彼女を裏切り、失望させた。
『ゆか』も同じなのだろう。
残念ながら、そのときの僕はあまり酔っぱらってはいなかった。
恐ろしいほどに会話が弾まない。
名前・年齢・職業・住んでいる場所・誰と来てるか。
これだけ聞くと僕はもう話すことがなくなるのだ。
ゆかはきっと以前の僕を期待したのだろう。
けど、その僕はそこにはいなかった。
そこにはただのコミュ障がいるだけなのだ。

そう言って、彼女は僕の元から去って行った。
僕は彼女の言葉を信じてはいない。
きっと僕の元から離れる言い訳を言っただけなのだ。
それを知っている僕は彼女を引き止めることも、存在しないつぶれた友人を一緒に助けに行く提案などはしない。
そんな無粋なことはしない。
つまらない人間と思われることはかまわない。
けれど、しつこいと思われるのは僕の意識次第で避けることができる。
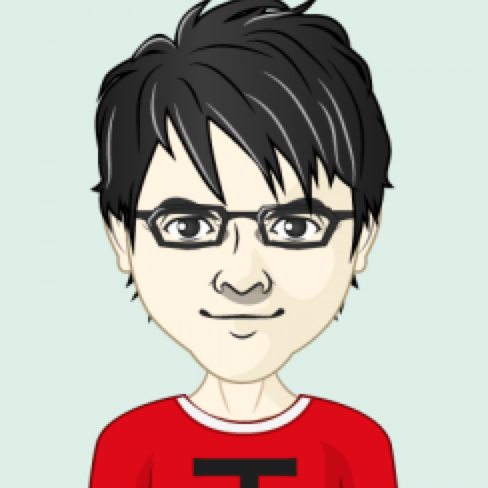
煌びやかなLEDライトが光る、低く開放感のない天井を見上げ、僕はそっとつぶやいた。
スポンサードサーチ
終焉のとき
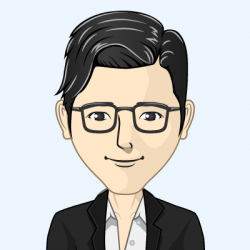
『K』と僕はなれ合いで一緒にいるわけではない。
一緒に帰るときは彼が女性と一緒にいないとき。
一緒に帰らないときは彼だけが女性を連れ出すことに成功したとき。
僕と再度会うつもりもないのに、彼はそう連絡してくる。
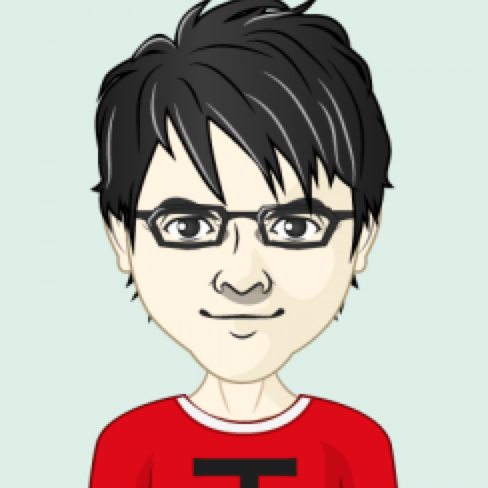
そんな彼に不満はない。
むしろ、僕は助かっている。
以前に彼が複数の女性と出ることとなり、僕も誘われた。
そのときの僕の居心地の悪さは忘れもしない。
あの状況におかれるぐらいならば、一人でクラブで踊っている方が楽しい。
言葉にせずとも『K』はそんな僕の気持ちを察してくれ、それ以来は先に一人で出て行くようになった。
ただ、そのときの時間はもう既に5時近くだった。
僕自身も帰路につかなければならない。
僕はダンスは好きだが、帰りは少し早めに帰るようにしている。
出る際にスムーズに出るには、クローズの少し前に出ないといけないからだ。
誤って、最後まで出ないと、大変なことになる。
その日に出会い、気持ちの盛り上がった男女、声をかけられうんざりしている女性、何も結果を残せなかったことを笑いながら話す男性グループ。
その結果に差はあれど、多くのコミュニティが混在するそのときに、一人で店から出るのはあまりにも心に芳しくない影響を与える。
僕は最後にもう一杯ジントニックを頼み、その場で空にしてグラスをおいた。
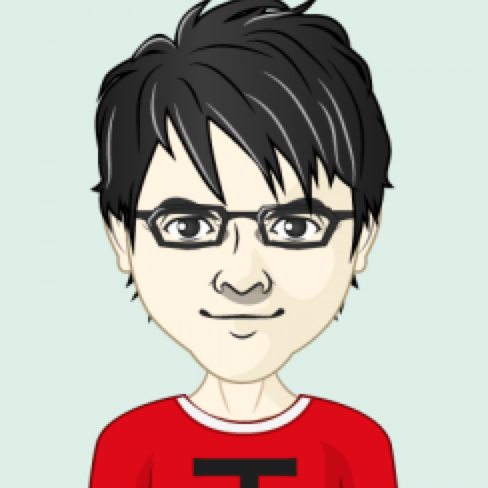
そう思い、店を出た。
僕の夜は終わらない。
店を出るときは決まって、少しきょろきょろしてしまう。
もしくは電話をしている振りをする。
まるで、誰かとはぐれて、合流しようとしているかのように振る舞ってしまう。
誰も僕を気にしてないことはわかってる。
けど、それでも、社会的に孤立している人だと思われたくない僕の小さな思いが自然とその行動に移させる。
いつも通り、僕は誰も探していないのに探していた。

探していないにも関わらず、僕は『ゆか』に再会した。
ゆかはミューズの目の前にあるコンビニから出てきたところだった。
その手には500mlの水があった。
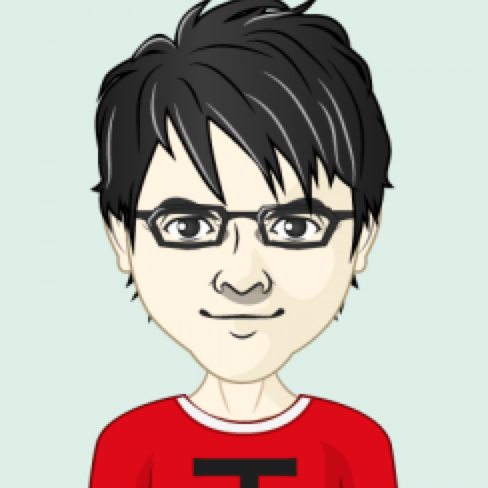
彼女の存在しないはずの、泥酔した友達を形式上心配した。
たとえ、もう平気そうにしてたとしても酔いが醒めたことにすればいい。
僕は彼女の嘘に気づかないふりして、事を終わらせようしてた。

彼女が俯き加減に困った顔をしている。
僕にとっては意外な反応だった。
予想外な反応に戸惑いながら、『ゆか』が僕の手を引っ張って行く。
その先には倒れてる女性がいた。

彼女の名前は『あやの』。
『ゆか』の泥酔した友達だった。
僕は不謹慎ながら、少しうれしい気持ちになった。
彼女が僕から離れた理由は、言い訳は嘘ではなく、事実だったのだ。
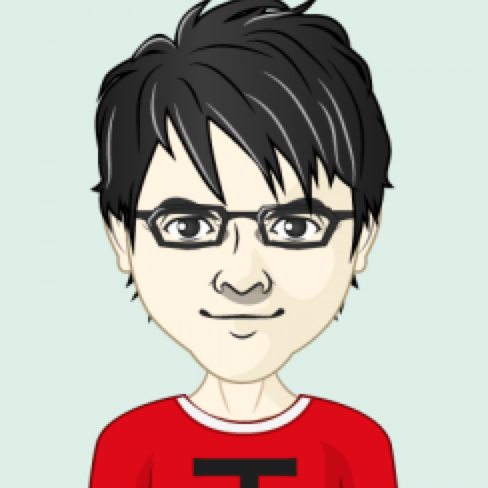
僕は、『ゆか』に対して好感を抱いていた。
僕が勝手に嘘をついたと思い、『ゆか』を自分勝手に解釈した罪滅ぼしだったのかもしれない。
『ゆか』がきちんと友達を送り届けられるようにしてあげようと思った。
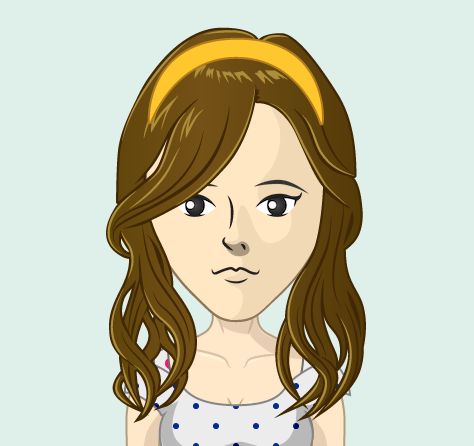
『あやの』は泥酔して、もう訳がわかんなくなっていた。
タクシーに乗る事を拒否し、飲食店や近くのホテルに入る事も拒む。
『あやの』が唯一僕らに伝えた事は一つだった。
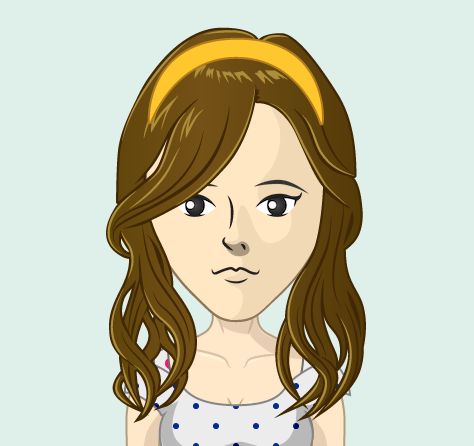
それが彼女の最後の言葉だった。
まるで遺言かのようにそう言ったあとに彼女は再び動かなくなったのだ。
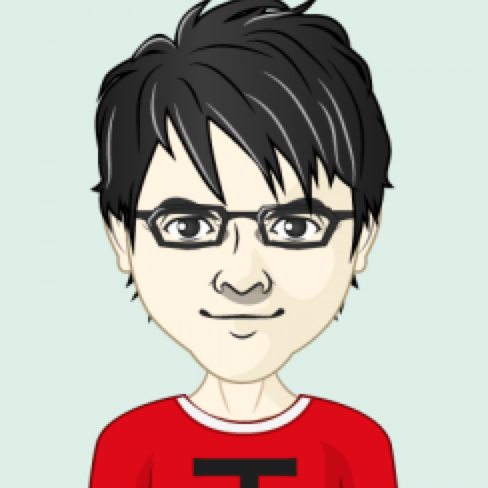

僕は少しドキッとした。
それは恋心など淡いものではなく、自分の家と全くの逆方向だったからだ。
僕は『あやの』に肩をまわし、駅まで運んだ。
そして、『ゆか』は『あやの』を自宅まで送り届けると言った。
僕はなぜか、自分も同じ方向だからと嘘をついた。
僕の運命
電車に乗ってからはどうしようもなかった。
途中で何度も帰ろうかと思った。
起きながらも、自分の家とどんどん離れて行くことに不思議な気持ちになった。
しかし、目の前の二人はそれを許してはくれなかった。
なぜならば、二人とも電車で爆睡していたからだ。
可愛い姿で眠っているなら微笑ましいだろう。
しかし、彼女たちは家のソファで寝てるかのごとく、倒れていた。
どうしたら、彼女たちを放置できるのだろうか。
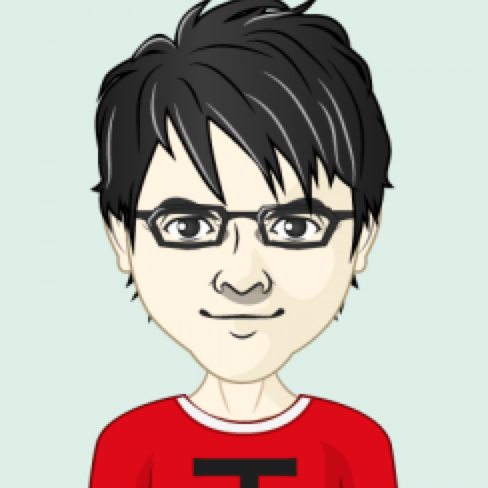
『あやの』の家の最寄り駅までの時間だった。
僕だって眠くない訳ではない。
けれど、ここでも僕が寝たら寝過ごす事が確約されてしまう。
僕は小説を読んだり、『K』とメールをすることで時間を過ごしてた。
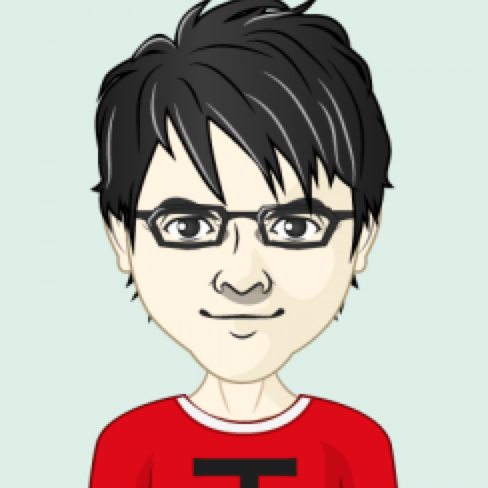
嘘はついていない。
嘘発見機を使われたとしても、それが高性能であれば、僕が嘘をついていないことが証明される。
ただし、それが真実なのか。と言われれば疑問がよぎる。
それでも僕は『クラブで知り合った女性と女性の家に向かっている』
という男性なら誰しもが憧れるシチュエーションの真っ只中であることは間違いなかった。
その日に読んでいた小説は『君の膵臓を食べたい』。
小説の物語と現実の僕のギャップは、理性を壊しそうだった。
到着駅の直前で、僕は『ゆか』を起こした。

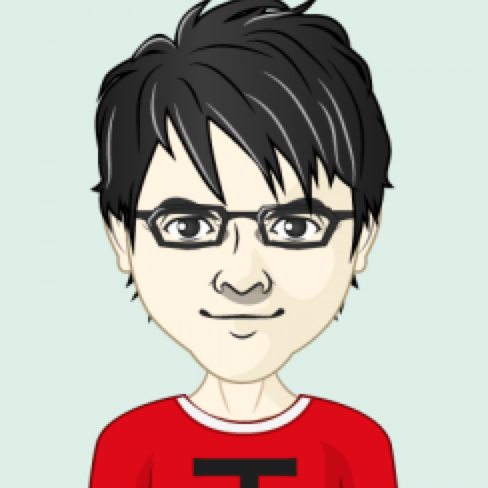
世の中にはついていい嘘もあると思う。
少なくとも僕のついた嘘は決して悪い嘘ではないと今でも自負している。
僕らは『あやの』の免許証を頼りに彼女の家にたどり着いた。
とても綺麗で整頓されている部屋は僕の部屋とは大違いだった。
1Kの広めの部屋は一人暮らしには十分な広さだった。
最後にあやのをベッドの上に寝転ばせ、途中の自販機で買ったお茶を一口飲んだ。
横ですやすやと寝ている『あやの』の顔はとても心地良さそうだった。
そういえば、『あやの』の顔を見たのはこのときが初めてだったかもしれない。
そう思ったら少しおもしろくて笑ってしまった。

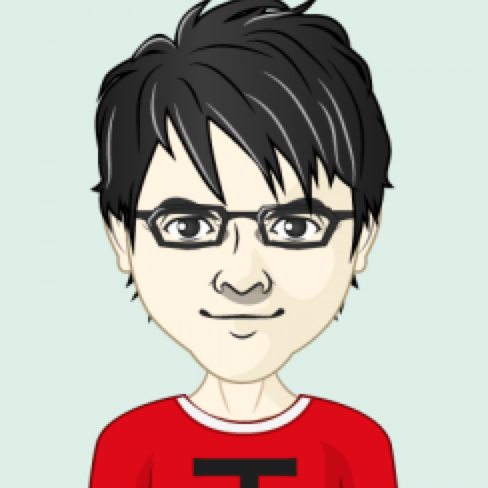
『あやの』の部屋を出て、僕は帰るため、リビングのドアを開け、そっと音が鳴らないように静かに閉めた。
靴を履いて、玄関から出ようとしたそのときに、閉めたはずのリビングのドアが開いた。

良い人ぶるわけではないが、そんな言葉をもらえることにも少しうれしかった。
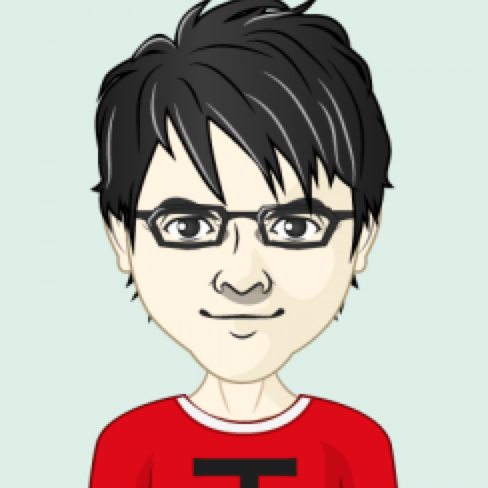
『ゆか』に背を向けたまま、座って靴を履いていると『ゆか』が僕に近づいてきた。
立ち上がると背中の近くに『ゆか』を感じた。
僕の心が大きく動揺したのがわかった。
きっと振り向けば彼女は、抱きしめる事もできるほどに近い距離にいることがわかってた。
そんなときに振り向いて言葉を交わせるならば、こんな生き方はしていないだろう。
僕は彼女に背を向けたまま立ち上がり、玄関から出ようとした。
そんな僕を引き止めるように『ゆか』が僕に話しかけてきた。

なんかあの日と全然違いますもんね笑。
『ゆか』がどんな顔してそう言っているのかはわからなかった。
ただ、そこには悪意ではなく、好意に近いものがあることだけはわかった。

けど、べんさんそのあと連絡先も聞いてくれないから、遊ばれちゃったと思ってたんです。
いったい『ゆか』は何を話しているのだろうか。
それは本当に僕だったのか。
いや、僕だったとしよう。
いや、僕なのか?
動揺する僕に『ゆか』は続けて言ってきた。

何か『ゆか』に言わなければならない。
僕は『ゆか』をどう思っているか答えはでない。
少なくとも嫌な印象は受けていない。
むしろ、好感を持っているとすら言える。
『あやの』をここまで送り届け、そのことに嫌な顔ひとつしていない子だ。
そして、何よりも僕に声をかけてくれた。
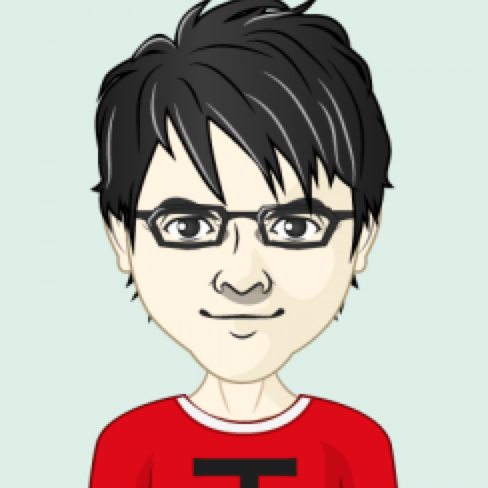
僕は『ゆか』の方を向く決意をした。
いや、細かい理由はない。
人と話すときは相手の顔を見るべきだ。
ただ、それだけだった。
人として自然にそう振り向いたときに、『ゆか』は僕が思っていたよりも近くに立っていた。

『ゆか』がいたずらな笑顔を浮かべながら、僕にそう言ったとき。
『ゆか』が喋ったときに出る息づかいを感じる。
『ゆか』の体温を服越しに感じる。
『ゆか』はどうしてもこんなにも僕の近くにいるのだろうか。
僕だって鈍感ではない。
いや、こうまでされないと気づかないのだから、鈍感なのかもしれない。
きっと今彼女を抱きしめても、キスをしても、きっと彼女は受け入れてくれるかもしれない。
本気でそう思った。
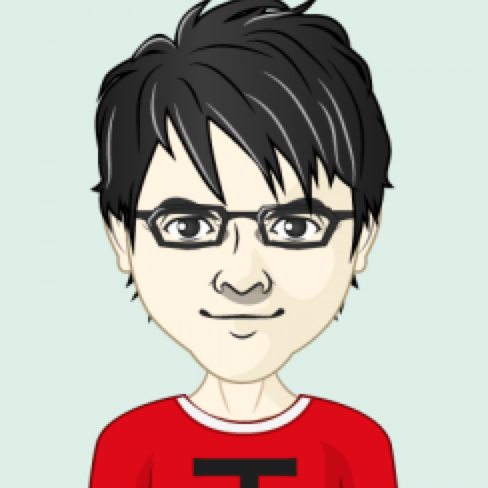
そう言った僕に対して、『ゆか』は少し不服そうだったが、部屋に戻り、携帯電話を取りに行った。
LINEのQRコードで連絡先を交換し、『ゆか』に別れを告げた。

次会うときは絶対酔っぱらってもらいますから笑。
そういった彼女はとても魅力的だった。
僕も一緒に飲みに行けるときが楽しみだった。
もしかしたら、彼女ができるかもしれない。
そんな風に思いながら、『あやの』の家から駅に向かい、帰路に着いた。
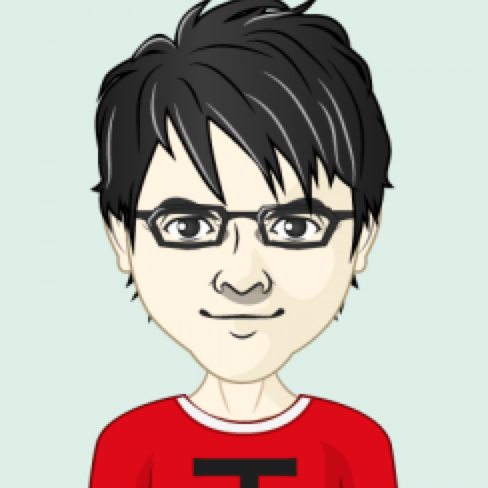
その遠さに絶望しながらも、『ゆか』との出会いはそれを忘れさせてしまうものだった。
僕はこのとき、既に『ゆか』に恋をしてたのかもしれない。
その日だけ、気持ちが高ぶったのかもしれない。
お互い酔いが醒めれば、飲みに行く事も忘れてしまうかもしれない
けど、それから電車に乗っている帰り道、僕らはずっと連絡を取り続け、飲みに行く約束をした。
帰りの電車の中で僕のポケットから、ドリンクチケットが出てきた。
いつもなら、損をした気分になるが、その日は気にならなかった。
最後に伝えたいこと
みなさん、ここまで読んでくれてありがとうございます。
『泥酔した女性とべんの物語』はどうでしたか?
楽しんでいただけたならよかったです。
今回は小説風に書いてみました。
みなさんもお酒を飲むときは気をつけましょう。
泥酔するとみんなに迷惑かけちゃいます。知らない人にもね!
ただ、そんな中、すてきな出会いがあるのかもしれません。
ちなみに、『ゆか』と飲みに行く約束ですが、あれはちょっと物語を盛り上げるためについた嘘です。
けど、帰りにずっと電車の中でLINEしてたってのは嘘です。
そういえば、連絡先を交換したってのも嘘です。
『ゆか』が僕がすごい近い距離で話をしてたってのはガチで嘘です。
前にクラブで会って飲んだのですが、その時にキスしたっていうことだけは嘘です。

ってところまでは本当にあったことで、その下に書いてあるのはそれこそ全部嘘です。
それでも電車に乗って帰ってるときに、ポケットからドリンクチケットが2枚出てきたのは本当です。
世界の『幸と不幸』はマイナスだった。
その不幸は僕にだけ降り掛かってた。
誰か僕に幸せをください。
見てるか『K』?これがあの日にあった真実の物語です。
女の子と一緒に帰ったのは事実なので、べんはお持ち帰りに成功したといっても過言でありません。
べんは女の子をお持ち帰りしながらも、連絡先も聞かずに別れるプレイボーイだったのです。
完(続かない)










